ニュース
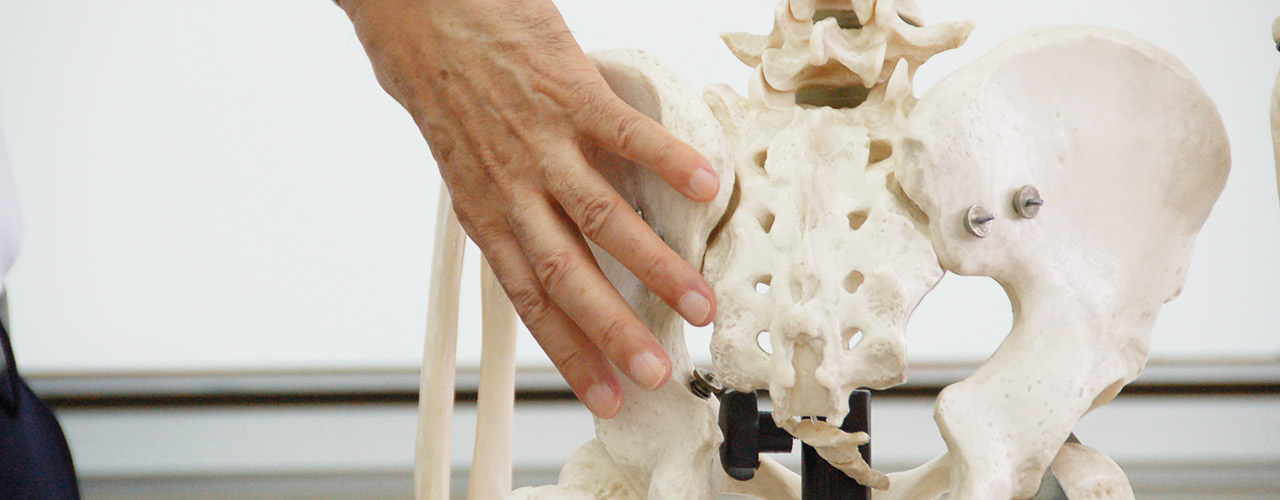
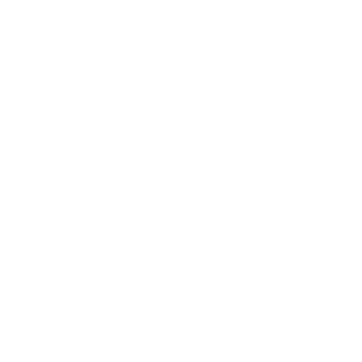
AKAPTOT会ニュース第65号(2022年5月)
2023.7.19
日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会ニュース
Vol.65 2022.5
『会員の皆様へ』
日本関節運動学的アプローチ医学会理学・作業療法士会
理事長 農端芳之
2000年から日本関節運動学的アプローチ医学会理学・作業療法士会(以下AKA-PT・OT会と略す)が発足し活動が開始され、今年で、23年目を迎えています。2020年度の事業計画は、学術集会(山梨)開催、AKA-PT・OT会会誌発刊、ニュース発行(年3回)と研修会が地域技術研修会36回、紹介コース7回、基礎コース1回(10日)、フォローアップコース1回(2日)、応用コース1回(2日)受験コース2回(前後期各2日)、伝達講習会14回(1日)、延べ開催日数が75日を計画していました。
当会の研修は一つのベッドの周りに3~6人が囲み、受講者同士で技術練習を行い指導者が指導する形式が基本でした。指導方法も口頭で指導するばかりでなく、技術のデモンストレーションをしたり、手から手へ伝えたり身体接触を伴うのが基本でした。受講者・指導者が密集し会話するという、感染対策とは真逆の方法で行っていました。
このような状況で2019年の秋からCOVID-19がまん延し、2020年度は、各種の研修会を中止し、学術集会が延期となりました。活動としては、AKA-PT・OT会会誌発刊、ニュース発行(年3回)に止まりました。2021年度も同様に各種の研修会は中止になりました。学術集会は準備を続けていましたが、状況を鑑み対面式やリモートでの開催が出来なくなりました。しかし、学術集会会長のご努力により、学術集会でのプログラム内容を学会誌に執筆して頂き、会誌の紙面上で学術集会を代替する事になりました。学術集会開催が出来ない、苦肉の策になっています。
そこで、このままではあまりにも会員とのコミュニケーション不足が顕著になりますので、新たな試みとして、2021年春から過去の学術集会における教育講演の内容をWebで公開するようにいたしました。皆様の向学心に少しでもお応えできれば、この上ない幸せです。
2019年末から現在まで緊急事態宣言や蔓延防止策の発出などが繰り返され、人々と接触する活動が制限されました。特に医療職は自重が求められ、抑鬱された気持ちの日々が続いているかと愚察していました。
ところが、JPTANEWS、2021.12Vol.334によりますと不自由な環境下でも、多くのPTは学習意欲を損なわず自己研鑽に努力しているという報告がありました。PT・OT皆様の向学心や向上心に、勇気を得て歓喜しました。
そこで、当会の新たな試みとして、AKA-PT・OT会は皆様の情熱に応えられるよう研修を計画しています。
研修は対面でしか行えない内容とWeb上で十分行えることを整理して実施しようと考えています。対面で研修会が行えるような状況になるまでは、動画配信などWeb上で行えることから始めたいと考えています。
主な内容は、
1.AKA-博田法と運動療法(AKA-博田法は元来、運動療法に不足している部分を補った方法で、運動療法がどのように修正されたか。)について。
2.①AKA-Hと関節運動学、②AKA-Hの基礎、③評価と治療、④関節神経学概論について。
3.AKA‐博田法を行うことで得た知見について。①関節機能障害と関節機能異常、②関連痛、③関節受容器反射、④NDN、⑤軟部組織の収縮性と関節拘縮、⑥関節神経学的治療法(脳卒中の運動療法と機能訓練)、⑦AKA‐博田法の習得法・指導法。
4.臨床応用について(実際の臨床場面と効果の提示)。
です。準備が整い次第、発信したいと考えています。
まだまだ、先が見通せない様相で気が晴れない時間が続きそうですが、ご自愛のほど祈りいたします。
- 『お知らせ』
本会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大・予防の観点から現況では「対面式の実技研修会」について中止または延期となっております。現時点での2022年度の決定事業は第22回学術集会(福岡)の開催、会誌の発刊、ニュースの発行、過去の学術集会動画配信に加えまして新たな内容でのweb配信が行えないか検討しております。引き続き感染状況を鑑みながら、様々な情報を収集し、また皆様の健康・安全面を考慮しつつ前向きに事業の推進を図って参る予定です。
現段階においては技術研修コースの参加をお考え、心待ちにされていた皆様のご期待に応えることができず大変心苦しいですが、何卒状況ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
- 第22回学術集会(福岡)開催のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中、第22回学術集会が福岡市で2022年10月10日(月・祝)に開催することになりました。
前回大阪での第20回から3年数か月ぶりの開催となることもあり、内容および開催形態含め、当会として新生的な学術集会となると考えられ、皆様にとりまして興味ある、充実したものと感じて頂けるよう準備委員一同少しずつ準備を進めております。感染状況など様々な状態に対応できるよう対策も練って参る所存です。
詳細については同封の案内をご覧下さい。また、学術集会専用サイトを立ち上げ、少しずつ情報をアップしておりますので随時チェックして頂き、是非広く情報拡散をお願い致します。
多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております.
- 学術集会開催要項
テーマ :「AKA-博田法のこれまでとこれから」
開催日時:2022年10月10日(月・祝)9:00~16:00(予定)
会場 :福岡国際会議場 国際会議室501 (2007年 第8回学術集会会場)
福岡県福岡市博多区石城町2-1 https://www.marinemesse.or.jp/congress/
開催形式:(予定)ハイブリット開催(対面式+web配信式)
コロナ感染状況により変更あり
- 令和4年度 認定試験(AKA‐博田法)の見通しについて
令和4年度の認定試験の実施については、4月現在では見通しがついていません。
4月に入って新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向を推移していましたが、収束に向かっているとはいえず、感染者数の高止まりから増加傾向に転じており第7波の感染拡大の兆しが報じられています。このようなコロナ禍で今年度も認定試験の実施は難しいと予測しています。
昨年の5月号のニュースにも記しましたが、認定試験を実施するには地域技術研修コース等の再開とセットで考えています。この対面式の集団研修が、このコロナ禍ではなかなか実行できないのが悩ましいところです。
今後も感染状況の推移とその対策を見ながら、研修企画と合わせて認定試験の再開の可否を検討していきます。
認定委員会 井端 康人
- 令和4年度 認定資格更新期間延長のお知らせ(認定委員会)
一昨年、昨年度(令和2、3年度)は当会事業が中止となり、単位取得が行えない状況でしたので資格更新期間の自動延長を行いました。
令和4年度も現状では学術集会以外の開催が未確定であり単位取得が行えないため、引き続き下記の通り更新期間の自動延長を行います。昨年度と同様に各自延長手続きの必要はありません。
~ 記 ~
対象者は以下の通り自動的に1年間の延長が付与されます。
- 対象:令和4年度に会に籍を置いている有資格者
- 令和4年度は更新期間5年に含めず単位取得期間を延長し令和2および3年度の延長とあわせ更新期間を8年間とする
- 令和5年度は事業の開催状況により再度更新期間の検討を行う
参考)更新期間附則(会誌Vol.12 2019)
次の場合は所定の手続きにより更新期間を延長することができる。
- 傷病等により会の活動へ参加が困難な場合
- 女子の妊娠、出産については係る期間
- 風水震火災、その他理事会が認めた事由で会の活動が困難な場合
上記で期間延長を希望する場合は延長事由を記載した書類を添え認定委員会へ申し出ること。
注 1)延長期間は年度毎とし、申請が年度途中であっても当該年度の単位は認定されない。
2)延長期間を終了し復帰する場合は速やかに認定委員会へ申し出ること。
- 動画配信サービスのお知らせ(再報)
動画配信担当 赤木 智(近畿ブロック)
昨年6月よりAKAPTOT会学術集会の動画をYouTubeで限定配信しております。新型コロナウイルスの感染拡大・予防の観点から当会の主な事業である研修会開催が困難な状況が続いている中、AKA‐博田法を学習できる数少ないコンテンツとなっております。プライバシーの問題もあり全てを配信することは困難ですが、皆様の日々の臨床の助けになればと思いますので、ぜひご利用ください。
以下視聴方法を案内します。
1、日本AKA医学会理学・作業療法士会ホームページにアクセス(http//akaptot.com/)
2、会員専用ページにログイン
3、その他の項目の動画配信をクリック
4、演題をクリックすると動画が視聴できます。
配信スケジュールは以下の通りとなっています。
| 配信時期 | AKAPTOT会学術集会 |
| 2021年6月1日~
(現在配信中) |
2019年 第20回学術集会(大阪)
AKA-博田法・ANT 未来(明日)への道標 |
| 2021年9月1日~
(現在配信中) |
2018年 第19回学術集会(愛知)
臨床力を高める |
| 2021年12月1日~
(現在配信中) |
2017年 第18回学術集会(山口)
AKA-博田法・ANTと動作 |
| 2022年3月1日~(現在配信中) | 2016年 第17回学術集会(福岡)
専門職として存続するために~評価と治療の妥当性~ |
| 2022年6月1日~ | 2015年 第16回学術集会(神奈川)
運動療法と関節の機能 |
- リレーコラム(第24回)
『ひとりごと』
関東甲信越ブロック
踊場さかいだクリニック
指導者助手 村上和則
今回のリレーコラムはテーマ毎に書き記そうと思います。興味のあるところを見ていただければ幸いです。
1,「AKAとの出会い」について書いてあります。
2,「最近の経験」としてコロナ禍で気付いたこと、経験したことを書いてあります。
3,「これからの事(思うところ)」として将来の希望について書いてあります。
- AKAとの出会い
①「AKA」という言葉を最初に聞いたのは学生の時です。当時、評価実習先の先生がAKAの研修会に参加され、学生の私に「AKAって聞いたことある?」と話されたことが最初になります。肩関節を診ていただき、可動域の変化を感じることができ「関節」を観察することの楽しさを体験しました。実習で実際に患者さんの関節可動域の測定を行い、授業で学んだ構成運動の中の「滑り・転がり・軸回旋」などを意識し、様々な関節の動きの複雑さに感動しながら過ごしたことを覚えています。評価・臨床実習で関節可動域の測定のたびに可動域の変化が生じ、その意味を知りたくて文献等を漁っても「これ!!」という答えが見つからず、測定者である自分の技術に問題があるのでは?と考察に記し、当時の指導者に「数回施行し、平均値を記載すると良いのでは?」または「最初の測定値を記載し、数回行うと可動域訓練を実施した後と同じことだから良くなるのは当然だよね」とアドバイスを頂いて半分納得(可動域が狭くなる方もいたので・・・)していた事も思い出されます。
②AKAの医学書との出会いは実習先の先生にお借りしたのが最初です。わくわくしながら中身を拝見させていただき興味が沸き、「ブルーとオレンジ色のAKAとデザインされた本(第1版)」という手がかりを覚え、夏休みに茨城のおじさんの家にお邪魔した時、東京見物に行った際に神保町・本屋街で見つけ購入したのを今でも鮮明に覚えています。国家試験後、晴れて理学療法士になり就職で関東に出てくる際もこの本を大切に抱えてきました。
③AKAを必要とした瞬間は就職後1年が経過する頃です。就職後は学生の時に学んだ事を実際の患者さんに時間の許す限り実施していました。例えば膝の術後の患者さんの関節可動域訓練は膝の付随回旋を説明し意識させ屈曲・伸展運動を行っていました。その頃は痛みが多少あっても頑張って運動を行っていましたが、同時期の術後の患者さんより可動域の改善が早かった覚えがありそれが自分の訓練内容が間違っていないという自信に繋がりました。そのような日々が継続し1年が経過した頃、当時派遣先の療養型病床での出来事がもう一度AKAを見直すきっかけとなりました。ある脳血管疾患後遺症の患者さんを担当した時です。患者さんが車いす上で自分の麻痺した指を一生懸命に動かしていました。「リハビリの先生に「手が臭くならないようによく動かすんだよ」って言われたから頑張っているんだ」との事。よく見ると手指の関節はだいぶ破壊が進み、リウマチの方のような短縮を起こしている状態でした。痙性麻痺が強く痛みを我慢して過度な可動域運動を長期間行った為にそうなったようでした。その手を見た時、関節の動きを理解し正しい動かし方と動かす範囲を指導すればこのような状態にはならなかったのでは?という思いがあり、もう一度AKAの医学書を見直すきっかけになりました。四肢の関節の構造・動かし方について医学書を参考に患者さんへ実施したり、動きを患者さんへ指導し自主訓練へ取り入れたりし、それなりの効果を実感する事が出来ていました。そのような中、病院長がAKAを腰痛の治療で用い始め仙腸関節を2人がかりで一生懸命動かすときに助手で参加し「仙腸関節」について学ぶ機会を得ました。徐々に四肢の関節→体幹の関節へのアプローチが四肢の痙性を減弱する効果を実感できたり、痛みの治療では痛みや痛みによる軟部組織の過緊張を減弱することを目の当たりにし、私にとって必要な技術だと確信しました。
- 最近の経験
新型コロナウイルス感染症の発生から丸2年が経過しました。その間、AKAPTOT会の研修会や学会が残念ながら中止となり、合わせて身近な勉強会も中止となっている状態が続いています。気が付くと1日が「ただ過ぎていくだけの毎日」となっていました。患者さんに全力を傾けている「つもり」となっていたかもしれません。「痛み」を主訴として通院されている方が大半ですので評価・治療を行い効果の確認次第、次回の予約を取るという一連の流れを繰り返していました。
そこで原点に立ち返り、患者さんの訴えの聞き取り・動作分析から時間の許す限り仙腸関節だけでなく、様々な関節を評価することとし問題点を掘り起こしました。ご年配の方は特に関節の変形だけではなく拘縮もよく見られ、これらの拘縮を治療することにより患者さんの利益につながりました。また自分自身の技術の再確認・改善にも寄与されました。
1例ですが紹介したいと思います(症例報告ではないので詳細はご容赦ください)。
症例:85歳 男性
主訴:腰痛、歩行開始10分で疼痛が出現し歩くのが辛くなる。
初期:治療はAKA博田法により仙腸関節・腰椎椎間関節を行う。(1回/2~3週)高齢ということもあり、仙腸関節の拘縮が強くこれが改善可能か評価・治療を開始した。SLR・FAD・FABは改善し、自覚的にも調子が改善する。
経過1:治療直後は関節可動域の改善もあり自覚的所見も改善するが、
①SLR・FAD・FABが次回治療時には数値的に戻る。
②歩行開始10分で疼痛が出現することに変化がない。(痛みがあるが我慢して歩いている)という状態で「治療」というよりは「対症療法」となっていた。そこで以下の評価を追加。
立位:踵荷重で後方(背側)変位がある。補正のために上体(胸部付近)は前方へ変位。
歩容:立脚中期から前足部への体重移動がほぼ無く股関節の屈曲で振り出しが行われる(ロボット様)。歩幅の減少とスピードが遅い。
以上より、下肢の関節可動域を検査し
①足関節の底背屈制限、足趾の屈曲制限が認められた。
経過2:仙腸関節・腰椎椎間関節に加えて距舟・距骨下関節、足趾の各関節の副運動技術および足趾の構成運動技術を加えて治療。
終了時:足関節・足趾の可動域制限の改善及び足趾の屈曲運動が改善した頃から、
①歩容の改善:立脚中期から足底部前方への体重移動が可能となる。軽度膝屈曲も見られるようになり、歩幅の改善とスピードの改善もあり。
②歩行開始10分での疼痛が消失し、1時間程度の散歩が可能となる。
③SLR・FAD・FABの数値が治療前後で変化が見られなくなった。
歩行時の疼痛が存在し指導として「なるべく痛みがあることは避けるように」としていた。しかし、本人は高齢ということもあり「歩かない(運動しない)と、弱っていくのが怖い」とあり、痛みを我慢して毎日の日課を継続していた。疼痛が関節可動域の狭小を作りその狭小が疼痛を助長するという痛みのループが出来ていたのか?と考えられた。可動域の改善により荷重・体重移動が正常に近くなり痛みによる余分な過緊張を作らず疼痛が改善し、自然な歩行が獲得された。良好なループができたことにより1時間程度の散歩が疼痛なく可能となった。
足部へのアプローチにより関節の一次性・二次性機能異常が解決され(可動域の問題解決、関節からの感覚入力の正常化、運動の再教育による最適化)全体的に好循環が起こり、仙腸関節・腰椎椎間関節部の軟部組織の過緊張が消失し、疼痛・歩容・歩行距離の改善が成されたと考える。
(尚、動作訓練、歩行訓練・指導は特に行っていません。自然に御自分で獲得したものです)
3,これからの事(思うところ)
今回、コロナ禍でいつも会える諸先生方にお会いできず、研修も受けられず、自分の行っていることが他者の目から見られることもなく過ごす状態となり、いつもとはかなり違う状況下で「内向き」に取り組んでみている真っ只中にこのコラムを担当させて頂きました。そのような中で前述2項目に記しましたが、自分のAKAに対する姿勢や取組が正しいかどうかはわかりませんが私が考えた事を記したいと思います。
私たちの仕事では「関節」を確認することは必須と思いますが、如何でしょうか?
では、その「関節」をしっかり評価できる方・治療までできる方はどの位いるでしょうか?
膝関節の可動域を確認するとき、鷲づかみにした下腿遠位を大腿後面に押し付けるように押しながら角度計を当てている人が大半ではないかと思います。同じように、足関節の背屈可動域運動(訓練)が踵を把持して同側上肢前腕で足底を一生懸命に押したり、腓腹筋をマッサージして緊張を下げている(つもり)方が未だ大半ではないでしょうか。
少なくとも、理学療法士・作業療法士の有資格者が【関節可動域検査・関節可動域運動(訓練)では普通に博田節夫先生の理論が使われるような時代】になっていけば良いなと思っています。
仙腸関節に限らず、自分が必要と考える関節に触れて・動きを観察し問題点が存在するかを判断し、治療により改善するかどうかを確認することが大切ではないかと思います。
関節包内運動に問題があるのか?その他に問題があるのか?私たち専門職の治療で解決するのか?医師による治療(投薬・手術・エコー下筋膜リリース等)でしか解決できないものか?を評価できるのはAKAだと思うからです。
例えば以下の疾患の患者様のように、評価・治療内容に関節可動域の関連が少ない場合でも、実際に評価・治療に加えることにより大分変化が望めるものもあると思います(根拠・証拠はありませんが)。
例1)呼吸器疾患の方には必要な評価に加えて、胸椎椎間関節・肋椎関節・胸肋関節・胸鎖関節・肩鎖関節・肩甲上腕関節の副運動をチェックし、加療→再評価を繰り返し行う。(可動域の改善から胸郭部の可動性が改善し、呼吸苦が減少するかも。)
例2)腹部術後の早期離床目的患者さんには、術創部疼痛評価および仙腸関節・椎間関節の副運動チェック・加療後、動作訓練・歩行訓練を行う。(二次性疼痛の改善により動作がスムーズに行えることにより、より早期に離床が可能となるかも)
筋力や耐久性も大切ですがもっと「関節」にスポットが当たるようになって欲しいと強く思います。
※会員外の方にはAKAPTOT会ホームページ:「AKA-博田法とは」を是非ご紹介下さい!!
4,最後に
今回は「ひとりごと」として、リレーコラムを書かせていただきました。
自分は何でAKAが必要だったか。普段何気なくできていた生活(研修会や勉強会で聞けていた事、教えてもらっていた事等)が出来なくなり、様々な制限の中で新しい情報を調べたり、勉強してみたり、自分なりに考えてみたり、実施してみたりで気付いたことがあったり・・・。新人さんや他のスタッフの訓練の様子を見ていて以前から思っていた事を改めて感じてみたり。と「気づき」について書いてみました。
色々、ご意見があると思います。例えば「症例はそもそも、仙腸関節の治療がきちんと出来ていれば問題なかったんじゃないの?」とか、「何を今さら、わかりきった事を言っているの?」など多々ありますでしょうか・・・。
今年こそは、少しずつでもコロナが収束し上記のようなご意見を直接お話し出来たり、活発な情報交換が気軽にできる年になって欲しいと思います。そして、戦争のない平和な世界がもっともっと継続して欲しいと心から願います。
それでは是非、学会等で見かけたときはお声がけしてください。よろしくお願い致します。
(大分、長文となってしまい申し訳ございません)
- 都道府県別会員数 849名(令和4年4月15日現在)
北海道 6 青森 1 秋田 4 岩手 4 宮城 5 山形 13
福島 4 茨城 3 栃木 28 群馬 11 埼玉 32 千葉 47
東京 54 神奈川106 新潟 1 富山 2 石川 1 福井 2
山梨 139 長野 6 静岡 21 岐阜 7 愛知 27 三重 1
京都 21 滋賀 9 奈良 14 和歌山 11 大阪 107 兵庫 27
岡山 10 広島 15 島根 5 鳥取 11 山口 46 徳島 25
高知 13 香川 19 愛媛 11 福岡 54 長崎 31 熊本 13
大分 13 宮崎 2 鹿児島 10 沖縄 10
- 日本AKA医学会理学・作業療法士会
事務局 E-mail : aka-pt@dream.ocn.ne.jp(お問合せはE-Mailでお願い致します)
(編集後記)
この度入会されました皆様、ご入会を誠にありがとうございます。冒頭の理事長挨拶にもありましたように「日本AKA医学会理学・作業療法士会」は国内・外の理学療法士・作業療法士に対するAKA-博田法の普及・発展を目的として1999年に発足され、23年が経過しています。この2年はコロナ禍で十分な活動ができておりませんが、学術集会や各種技術コース、認定試験、指導者の育成・認定等様々な事業を行ってきています。会員の多くは自分の手で患者さんを治したい、まずimpairment(機能障害)をしっかり治療したいという志を持った『臨床技術屋』の集団です。今後とも末永く宜しくお願い致します。